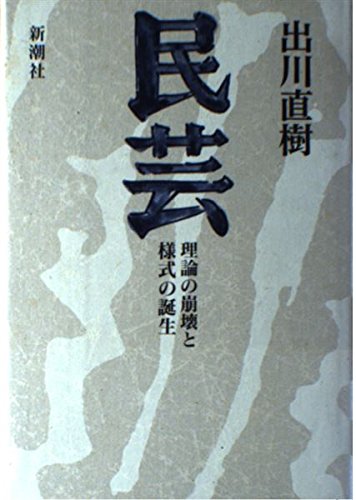友達と雑談していたとき、ふと「良い雑誌にはいろんな情報が載っているのに、誌面全体を貫く"世界観"があったよね」という話題になりました。ファッション誌とか音楽誌でも「○○系」という文化をつくり出し、読者はその世界観を通していろいろなものを学んでいました。この「編集された多様性」こそ、雑誌カルチャーの面白さだったと思います。(って友達が言ってて、自分はそこまで雑誌読んでなかったけど…w)
柳宗悦と民藝運動への違和感
そのP304の「日本の茶道の文化には、産地も時代も異なる器物を取合せて一つの有機体的な世界観を作るという理念があった(が柳宗悦が受け取れていなかった)」という内容がありました。私は民芸理論自体を批判が妥当なのかとかは分かりませんが、この内容は自分の中に残ってます。
要は、柳が掲げた “下手物の美” は 「自然な民衆の造形」を愛でる というような理念だったはずが、実際には"柳好み"のテイストを職人に指示して作らせた というズレがあった、という指摘です。この本ではむしろ民藝運動はアール・ヌーヴォーがやっていたように、明示的に既存のものを取り合わせて新しいスタイルを作っていく意識が必要だったんじゃないかと言われていました。
しかし個別的にみえる日本の「茶」を注意深く見れば、初代茶人やその伝統を継ぐものが、茶室という美の小宇宙の中で、全体への有機的なつながりという理念をいかに強く持っていたかが解る。「取合せ」という工夫がそれであり、その中で書画や各々の器物は注意深く互いの相乗効果をめざして取揃えられ、使われた。材質も色調も形態も異なる各々の取合せは単なる統一されたデザインのそれより表面的ではないが、一層高度な有機的な関係を持っていた。取合せは茶人の力量を示すものであり、茶会はその都度、茶室という全体に対する彼らの有機体系としての作品であった。
しかしここでも、柳がそこから受け取ったものは有機体系の理論ではなく、個別的な器への関心であり、名品を探り出す彼等の鋭い審美眼のみであった。
DJにおける「取り合わせ」と再解釈
DJ…というかなにか表現するときも、多分同じように既存のものを取り合わせて表現することが必要なはずです。例えば「電波ソング」というジャンルを取り上げるとしても、過去のジャンルの盛り上がりそのままではなく、その魂を今の時代や状況に合わせて再解釈・取捨選択して盛り上げるものだと思います。
その点やっぱりでんぱ組.incの世界観はすごかったと思っていて、音楽ジャンルを取り入れて毎回新しいことをやろうとしている上に、全体を通すとでんぱ組らしいワチャワチャ感(?)を表現していたように思います。例えば「ONE NATION UNDER THE DEMPA」とかディスコを入れたのはすごいなと。
じゃあ「魂」ってどうやればわかるんだって話があるんですが、それは自分もよくわかってなくて、それぞれが見極めていくしかないかなと思ってます。
ただ、こういうときに宗教の歴史の話は面白くてヒントになるパターンが多い気がしてます。例えばこの本は大乗仏教を「いろんな仏陀がいること」、密教をその発展として多中心的なものをその宗派の「魂(※って表現はしてなかったですが)」として受け取っていて面白かったです。そこまで詳しくないので、どれだけ妥当な受け取り方なのかとかはわからないんですが…。
自分にとっての中心ではあるけれども、絶対的な中心ではないことも理解している。こうした世界は、これまでよりずっと自由に感じられるでしょう。
また、ちょうど別の宗派(浄土宗系統)の本も読んでたんですが、共通する部分(いろんな仏陀がいること)もあれば全然違う発想の部分(他力本願や往相還相の考え方とか)もあって、「同じ経典を受け取ってもこんなに受け取り方やスタイルが違うんだ」と面白いです。だから同じジャンルを受け取る人によって「魂」は違っていて、それぞれ見出していくべきなんじゃないかとも思ってます。
まとめ:ズレを恐れず、編集者であれ
柳宗悦が抱えた「理念と実態の乖離」は、裏を返せば「編集の恣意性」をどう扱うかという永遠のテーマです。雑誌文化は 「取り合わせ」をあえて恣意的に行い、「○○系」という世界観で包む ことで成功してきました。DJ/イベント運営も同じく、小さな“誌面”を毎回つくる仕事だといえます。(ChatGPTにまとめてもらった文章)
だからこそ、ズレや偏りを恐れずに自分なりにジャンルの「魂」を見出しながら呼びかけることが、ジャンルを2025年の現在にアップデートする鍵になると思います。
そうすれば道に迷ったとき、他人のアドバイスを聞いても「この部分はnot for meだな」とあえて判断する勇気が出てくるんじゃないかなと思ってます。何の話だ。
もし同僚といい関係を築けてるなら、自分も相手もお互いに成長する関係を目指すべきだ。相手のフィードバックが正しいとは限らなくて、本当は10言われたうちの7くらいを取捨選択して受け入れるのでいい。そのためには相手の課題もあるが、自分の課題はチームでやりたいことが明確にしなきゃいけない。
— 黒めだか (@takeshi0406) 2025年5月5日
この間のイベントの「〇〇さんにとって萌え電波ソングとはなんですか?」って話があったんですが、自分は(少なくとも表面的には)ラブソングだと思ってなくて、予想外のことをして冗談を言いまくって相手を茶化すようなものだと受け取ってます。